これまでの記事でも、ご紹介してきましたが私は20代半ばから投資をおこなってきました。
これまでの記事でもご紹介した通り、20代・30代の頃の投資といえば「いかに増やすか」に意識が向いていました。
しかし50代を迎えた今、「いかに増やすか」と同じくらい「いかに減らさないか(守りの投資)」も重要だと感じています。
20代から30代前半までの投資では、特にルールなど決めずに感情で動いてしまっていた面があったと思います。
利益が出ればすぐに喜び、下がれば焦って売ってしまう。(利益確定も早過ぎて利益を最大化できなかったことも多かったと思います)
そんな経験を何度も繰り返しながら、結局は「安定して資産を増やす方法」が身につかないまま40代を迎えてしまったと感じています。
ここ数年思うのは、「取り戻せる時間」が限られているという現実です。
だからこそ、これからは感情ではなく“ルール”で投資を続けていこうと決めました。
今回の記事では、私自身の失敗や学びをもとに作り上げた「7つの投資ルール」を紹介します。

世界一周や海外移住など、人生の夢を実現するために「投資資産1億円」を目指しています。 「長期」「積立」「確信を得るまで分析する」投資を信条に、 ファイナンシャルプランナーの学習を通じて資産形成の本質を探り続けています。
投資ルールを決めた理由
感情のまま動く投資では、圧倒的な利益は出せない
正直に言えば、これまでの投資は“なんとなく”でした。
20代や30代のころは、日経新聞で話題になった企業に手を出したり、ニュースで注目される銘柄に飛びついたりすることがほとんどでした。
最近ではPER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、配当利回りなど、簡単な株価分析をするようになりましたが、それでもまだ甘かったと感じています。
条件に合う株を選んでも、利益が出たときも損をしたときも、特に明確なシナリオがないため、何の学びも残らないことが多かったのです。
そんなとき、成功した投資家の書籍『5年で1億貯める株式投資』や『5年で1億貯める株式投資』を読むと衝撃を受けました。
彼らは「なぜこの株が上がるのか」という明確な理由とシナリオを持って投資しているのです。
単なる数字や条件だけで株を選ぶのではなく、事業の成長性や市場の動き、人々の需要を読み解いて判断していました。
例えば飲食店なら実際に店舗を訪れて食べてみて、「これは伸びる」と確信できてから投資する。
そんな方法です。
確かに、私も「この株は伸びる」と確信して投資した時は伸びていました。

Amazonとアルファベット(Google)は、確実に伸びると確信を持って投資しました。結果、どちらの株も倍以上に伸びました。
50代からの投資は「取り戻せる時間」が限られている
20代や30代なら、失敗しても時間でカバーできます。
けれど50代になると、投資の失敗はそのまま老後の生活に直結します。
収入のピークが過ぎ、健康や家族のことも考え始めるこの時期に、
感情に左右された投資を続けるのは、もはや“ギャンブル”に近いと感じました。
そこで私は、あらためて投資の基礎を見直し、
「ルールで自分を守る」ことを決めたのです。
50代からの投資は「取り戻せる時間」が限られている
若いころの投資なら、最低限のリスク管理だけしておけば、失敗しても傷は浅く、経験値として次の投資に活かせます。
たとえば、20代で買った株が値下がりしても、給料やボーナスで補填しながら学びを得て、次の銘柄選びに反映させる──そんな余裕があります。時間が味方になってくれるのです。
しかし50代になると、投資の判断ミスや失敗はそのまま老後資金に直結します。
たとえば、定年までに1億円を目指す計画で、ここで数百万円の損失が出れば、取り戻すためにはさらにリスクの高い投資をするしかなくなります。
収入のピークも過ぎ、健康や家族のことも考えなければならないこの時期に、感情に任せて株を買ったり売ったりするのは、もはや“ギャンブル”に近いと痛感しました。
私はこの現実を前に、改めて投資の勝ち筋を見つけようと成功している投資家の書籍『5年で1億貯める株式投資』や『5年で1億貯める株式投資』を読みました。
そこで強く感じたのは、彼らはしっかり株式分析をして定量的な判断軸を持っていることと合わせて、必ず「この株はなぜ上がるのか」というシナリオを持って投資しているということです。
分析した指標はあくまで判断材料であり、最終的に勝敗を分けるのは、事業や市場、トレンドを理解した上での確信です。
具体的には、飲食店なら実際に店舗を訪れ、サービスや商品、顧客の反応を自分の目で確かめてから投資する。
小売やサービス業なら、日常生活の中でその企業の強みや成長性を肌で感じてから資金を動かす。
私もここから学び、投資の最大のルールを自分なりに決めました。
それは、「これは絶対に上がると確信を持てた株で勝負する」ことです。
数字だけに頼らず、実感と確信を伴った投資をする──これが、50代にして私が行き着いた投資方法です。
もちろん、それでもリスクはあると思います、でも自分が確信して投資すれば仮に失敗しても最大の学びが得られると思います。
次の章では、私が実践する具体的な7つの投資ルールについて順に紹介していきます。
私が決めた7つの投資ルール
1.これは絶対に上がると確信を持てた株で勝負する
投資の最大のルールは「これは絶対に上がると確信を持てた株で勝負する」です。
株式指標で対象株式をスクリーニングする部分は、これから研究していきます。しかし最終的には事業や市場の動向、成長性などまで分析した上で「これは絶対に上がる」と確信を持てる銘柄で勝負投資はおこないます。
具体的には、飲食店なら実際に店舗を訪れ、サービスや商品の質、顧客の反応を自分の目で確かめてから投資したいと思いますし、実際に利用できない銘柄は決算資料などを分析して「ビジネスモデル」「収益ポイント:などをしっかり把握して「これは絶対に上がる」と確信を持てるまでは勝負はしないこととしたいと思います。
2.ドルコスト平均法を前提とした積立投資
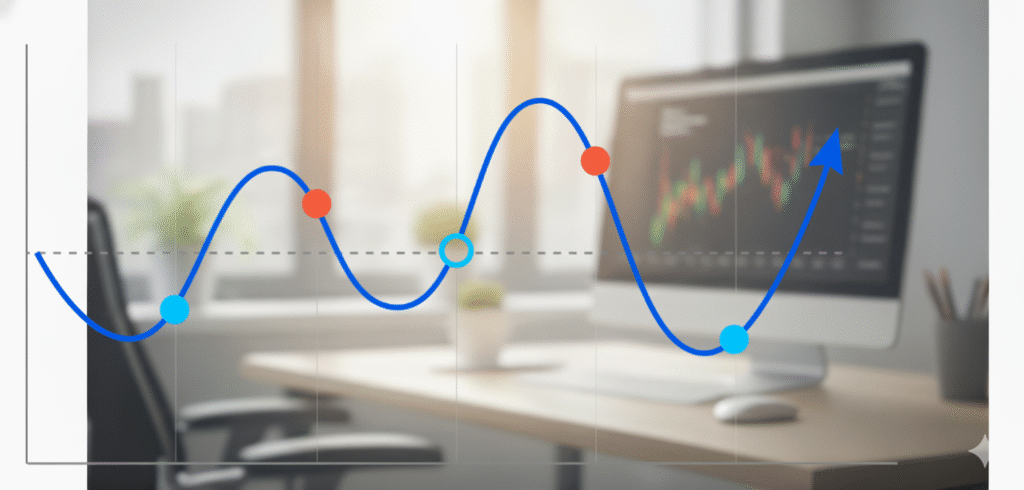
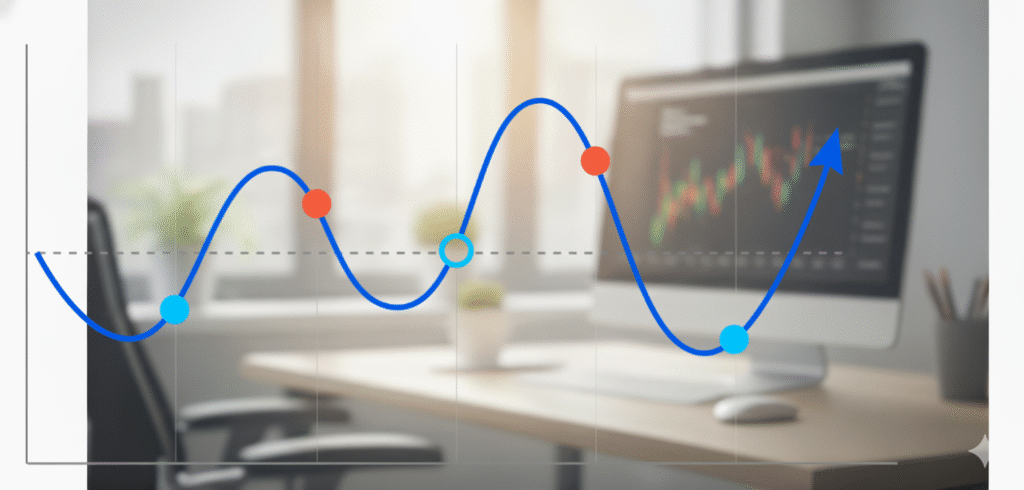
基本は「放置投資」。毎月の積立額を固定して淡々と続けることで、株価の上下に振り回されず長期的に平均購入価格を平準化する投資をおこないます。
このドルコスト平均法を前提とした積立投資で「ククレブ・アドバイザーズ」に投資していますが、現状トータルリターンが投資額の100%を越えています。こちらは積立投資なので積立開始時からは株価は3倍くらいになっています。
「ククレブ・アドバイザーズ」以外にも「property technologies」は投資額の50%強のリターン、「AnyMind」は投資額の30%強のリターンなど実績が出ています。
積立投資は「これは絶対に上がる」と確信が持てない状態でも少額で投資を続けて、損が出ても積立を停止することで最低限の損切になる投資だと感じます。(ドルコスト平均法的には安い時こそ多くの株を買うべきですが、ここ最近の経験から積立投資では「成長軌道に乗っていない場合」は積立停止することでリスクを最小化出来ている気がします)
3.分散投資
投資は、日本株、米国株、投資信託、FXなど、複数の資産に分散してリスクを最小化します。
さらに、ドルコスト平均法による積立投資も「時期の分散」と考えれば分散投資の一部です。
つまり、毎月少しずつ購入することで、株価変動の影響を平均化できます。
加えて、投資信託や日本株、米国株、FXの積立投資と、「これは絶対に上がると確信を持てた株で勝負する」投資を併用することも、重要な戦略です。
確信株への投資は集中投資の側面もありますが、他の積立や分散投資と組み合わせることで、全体としてのリスクをコントロールできます。
4.NISAを最大限活用
非課税枠を使い切ることで、税金分がそのまま利益になります。
特に50代からの投資では、節税=利益を守ることの意味が大きく、資産を着実に増やす上で重要です。
私の場合、勝負株への投資にもNISAを活用しています。
確信を持って選んだ株が成功すれば、利益は非課税となり、通常より大きく資産を伸ばせます。
ただし、NISAは頻繁に売買を繰り返す運用には向いていません。
そのため、どの銘柄をNISA枠で購入し、いつ売るのか──使い方の研究が重要です。
50代からの投資では、非課税メリットを最大限に活かしつつ、長期的な資産形成と勝負投資のバランスを意識しています。
5.損切りルールを決める
本業があるため損切りが必要な場面で、取引画面に張り付いてタイミングを見計らうようなことはできません。
そのため、勝負株の投資では「逆指値注文」などを使って損切りを自動予約するようにしています。
システム上であらかじめ「この価格まで下がったら自動的に売る」と設定しておくことで、感情に左右されず冷静に撤退できます。
勝負株の場合は大きな金額を動かすことを想定しているため、明確な基準を設定しています。
8%下落で損切りの「逆指値注文」の自動予約をしています。
一方で、積立投資の場合は毎回こうした注文を設定できないため、システム損切りには向きません。
その代わりに、私は積立投資では「だいたい10%下落で積み立て停止」を損切りの目安として積立停止としています。
淡々と続ける積立投資の中で、一定の下落幅をルール化しておくことで、精神的な負担を最小限に抑えています。
投資の種類や目的によって「損切り方法」を分けることで、50代からでもストレスを減らし、リスクをコントロールして長く投資を続けることができるようになると思います。
6.長期保有を基本にする
私の投資スタイルは、勝負株は中期(数ヶ月〜1年程度)での運用・勝負を前提としています。
短期の値動きで一喜一憂せず、ある程度の期間で結果を見極める方が、自分の性格にも合っています。
一方、それ以外の銘柄──つまり積立投資や安定銘柄への投資については、損切りルールに抵触しない限り、基本的に手放さない方針です。
株価が多少上下しても、長期的に右肩上がりで成長していく企業を信じて保有し続ける。
この「待つ姿勢」が、50代からの投資では最も重要だと感じています。
そのためには、中長期的に成長する企業を見極める視点が欠かせません。
一時的な流行や話題性よりも、企業のビジネスモデル・市場の成長性・経営者の姿勢などを重視して選びます。
時間を味方につけ、配当や優待を楽しみながら、少しずつ資産を育てていく──それが私の「長期保有」の基本方針です。
7.利益確定のルール化
「長期保有を基本にする」という前提ですが、勝負株に限定して利益確定のルール化を考えています。
積立投資や中長期で成長を見込む銘柄については、そもそも利確を目的としていません。
企業の成長とともに配当や優待を受け取りながら、長く保有していく方針です。
一方、勝負株では明確なシナリオと利益確定ラインを事前に設定して投資します。
「どのような展開で株価が上がるのか」「どの時点で売却するのか」を、購入前にシミュレーションしておくことで、感情に左右されない判断ができます。
もちろん、「もっと伸びたのに…」と後悔する場面もあるでしょう。
しかし、勝負株はあくまでアグレッシブな目標を持って挑戦する投資です。
利益が出た時点で欲張らず、計画通りに利確する──この“欲張りすぎない姿勢”が結果的には利益を最大化出来るのではないかと考えています。
ルールは現時点での仮ルール
ここまで紹介してきた7つのルールは、現時点の私にとっての“今の最適解”だと考えています。
けれど、これが永久不変のルールだとは全く思っていません。
投資環境は常に変化しています。
金利、為替、世界情勢、テクノロジー──数年、最近では数ヶ月単位で「常識」が大きく書き換わる世界です。
だからこそ、ルールもまた「固定化するものではなく、アップデートしていくもの」だと考えています。
実践してみて、初めて分かることがある
どんなに本を読んでも、実際に自分のお金を動かしてみなければ分からないことがあります。
「このルールは自分に合っているのか」
「ストレスを感じるポイントはどこか」
「想定外の値動きの時、自分はどう反応するのか」
それを知るためには、実践して検証するしかありません。
つまり、ルールは最初から完璧を目指すのではなく、“仮説”として動かしながら精度を上げていくものではないかと感じています。
投資は「自分を知るプロセス」でもある
投資において重要なのは、市場を読む力や企業分析力だけではありません。
自分の性格・判断傾向・ストレス耐性を理解することです。
ルールを決めて運用してみることで、はじめて「自分の投資スタイル」が見えてきます。
自分に合った「自分の投資スタイル」が見つかるまでは、だれかの真似をしたり、参考にしたりするのが良いと思います。
そんなとき、成功した投資家の書籍『5年で1億貯める株式投資』や『5年で1億貯める株式投資』も参考になると思います。
50代からの投資は、残り時間をどう使うかという“人生設計”にも直結します。
だからこそ、ルールを持ち、それを時々見直しながら、「自分をアップデートしていく姿勢」が大切なのではないかなと感じています。
まとめ
これまでの投資経験を振り返ると、若い頃は感情に左右され、利益確定も損切りも直感で行っていたため、安定した資産形成にはつながりませんでした。しかし50代を迎え、時間の制約や老後資金の重要性を考えると、感情任せの投資はリスクが高く、ルールに基づいた運用が不可欠だと感じています。
私が実践する7つの投資ルール
- 確信の持てる勝負株への投資
- ドルコスト平均法による積立
- 分散投資
- NISA活用
- 損切りルール
- 長期保有利益確定のルール化
は、単なる数字や条件だけでなく、事業や市場の成長性、実感を伴った確信を重視しています。これにより、リスクをコントロールしながら、精神的な負担を最小限に抑え、資産を着実に育てることができると考えています。
また、投資ルールは固定ではなく、環境や自分自身の変化に合わせてアップデートするものです。投資は単なる資産形成だけでなく、「自分を知るプロセス」でもあり、自分の性格や判断傾向を理解することで、より自分に合ったスタイルが見えてくると思います。
50代からの投資では、残された時間を意識しつつ、ルールに従って冷静に判断し、自分の投資スタイルを磨き続けることが、安定した資産形成と安心した老後への第一歩になるのではないでしょうか。
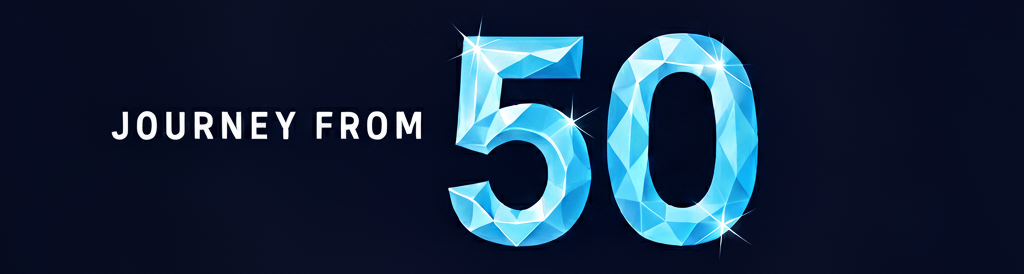
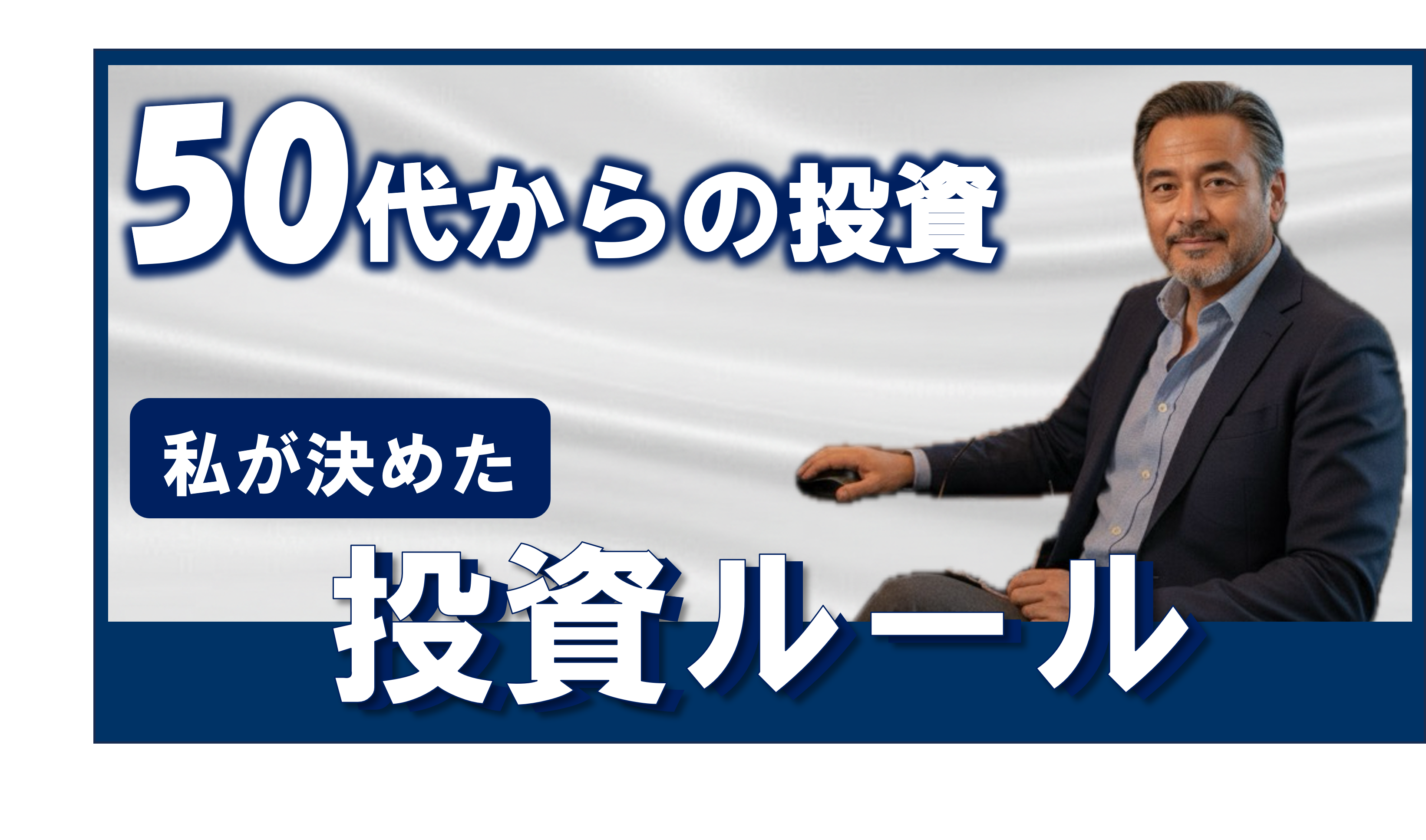



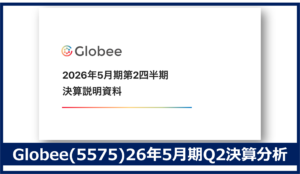
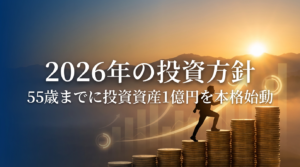
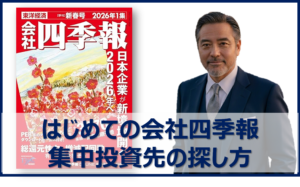
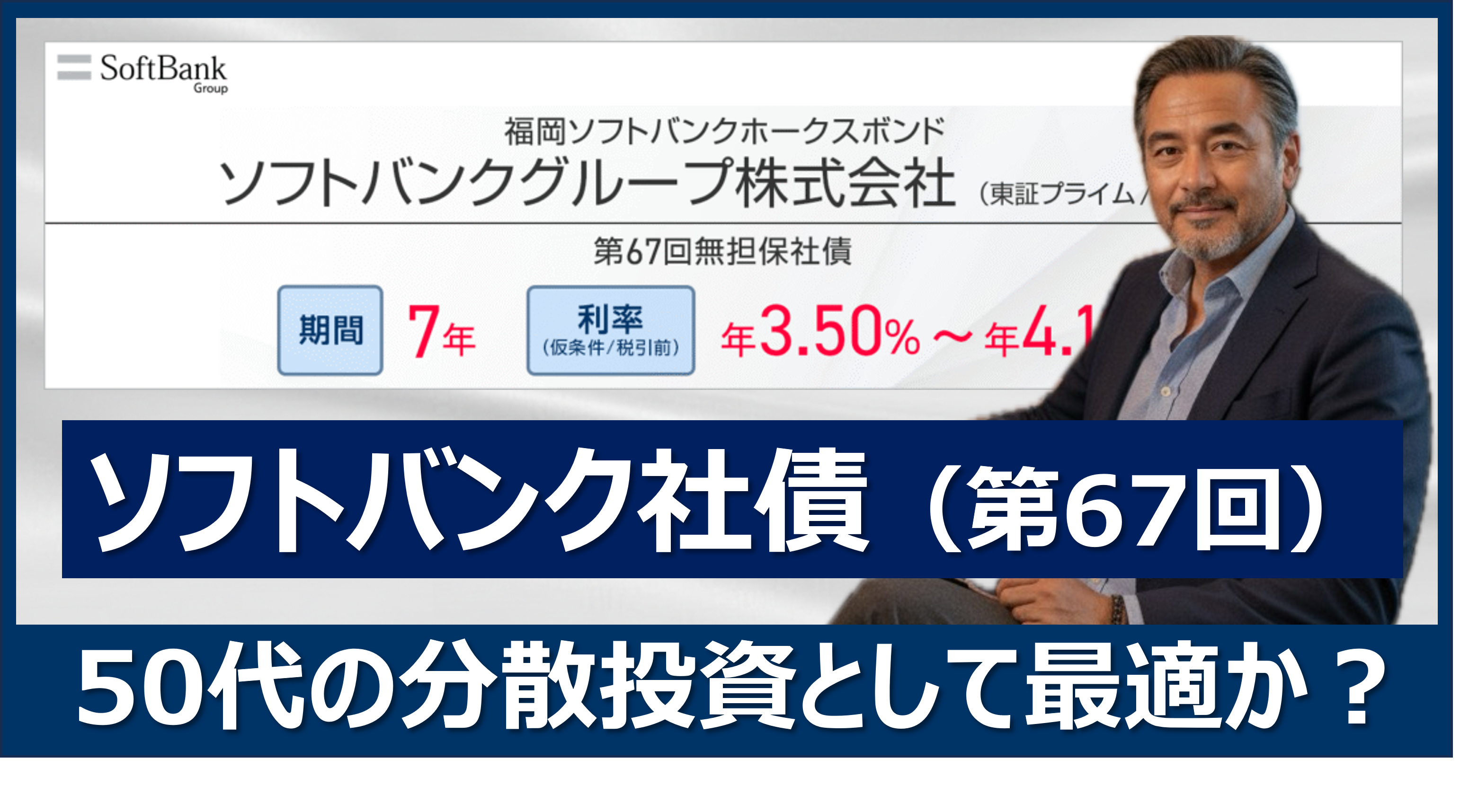

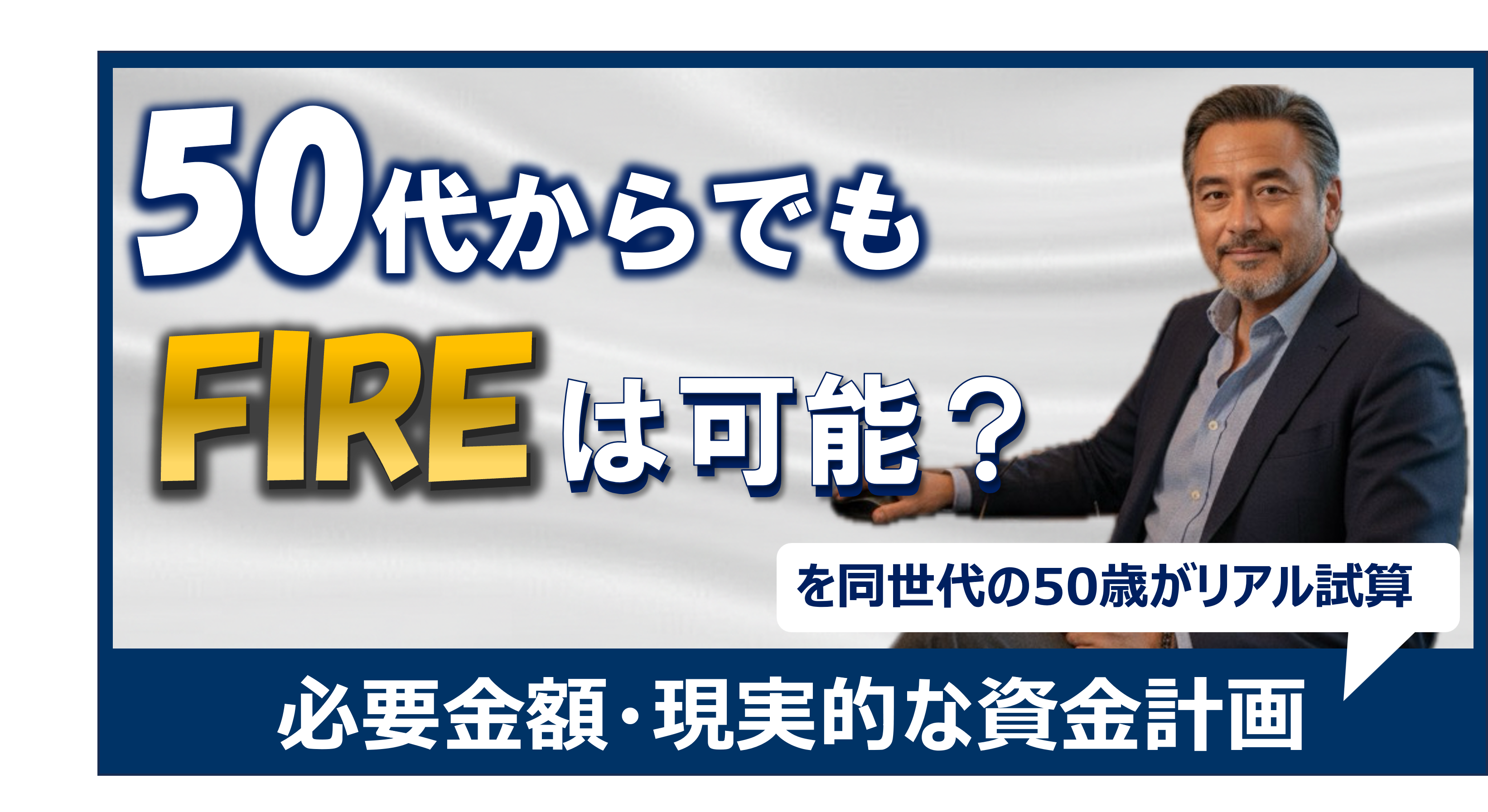

コメント